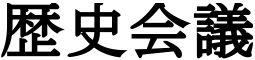「ジャパニーズ・ドリーム」
日本で成功したことを指す言葉です。
長い日本の歴史の中で最もジャパニーズ・ドリームを叶えた人といえば誰でしょうか?
江戸幕府を開いた徳川家康でしょうか?
明治維新を達成した維新三傑でしょうか?
はたまた、現代の成功者である孫正義でしょうか?
実はもっと成功した人がいるのです。
それが、今回の主人公である天下人「豊臣秀吉」です。
農民生まれ
豊臣秀吉の生まれについては色々な説があります。
数多ある説の中でも、最も有名は説が「農民出身説」ではないでしょうか。
本記事では、「農民出身説」を採用して執筆していきます。
父と母
生まれた場所は、尾張中村(現:名古屋市中村区)だと考えられています。
父は、織田家で足軽をしていた木下弥右衛門。
母は、美濃・関鍛治の刀工集団の一人である関弥五郎兼員の娘である御政所・仲です。
御政所・仲の妹は福島正則の母である松雲院だったり、従兄弟は加藤清正の母である聖林院と有名人の名がずらりと並びます。
母・御政所・仲は、父・木下弥右衛門の死後に竹阿弥と再婚しました。
これがまた秀吉は竹阿弥と仲が悪くて悪くて、14歳~15歳頃のときに家を出ます。
これが豊臣秀吉誕生への軌跡の第一歩でした。
松下家に仕える
一番最初に仕えたのが、駿河・今川家の家臣をしていた松下嘉兵衛之綱でした。
14歳~15歳頃の話です。
ある程度目をかけられ順調に奉公をしていたのですが、同じ家臣から虐められイビられと悲惨な目にあっていました。
見かねた松下嘉兵衛之綱は秀吉を追い出しました。
織田家に仕える
1554年(天文23年)
秀吉に転機が訪れます。
織田信長の小者(下男)として仕えることになります。
あらゆる雑用を引き受け成果を出し、頭角を現してきました。
後世の作り話らしいですが、有名な話の「藁草履の話」はこの頃です。
信長の草履取りを担当していた頃に、冷えきった草履を懐に入れて温めておいた話です。
1582年(天正10年)6月2日(中国平定と本能寺の変)
時を飛ばし、28年後の話です。
中国地方では、秀吉が、毛利輝元に仕える清水宗治が領主をしていた備中高松城を攻め落とすために、水攻めで追い込んでいました(高松城の水攻め)。
一方、京都では、織田信長が明智光秀の謀反により、京都・本能寺で自害しました。
日本最大の事変である「本能寺の変」です。
中国大返し

歌川豊宣 作「新撰太閤記 清水宗治切腹之図」
本能寺の変を知った秀吉は、領主・清水宗治の切腹を条件に早急に毛利輝元と和解し、京都へ軍を引き返します。
一刻も早く京都へ帰りたかった秀吉は、少しでも走るスピードを上げるため、重い鎧・兜は全て脱がせ、下着で走らせました。
また、ゆっくりと飲み食いする時間も惜しいため、道中の農民の家に頼み、水とおむすびを提供をさせたそうです。
現代の配達技術でも2~3日かかるにも関わらず、秀吉は10日で京都へ帰ってきました。
天下統一までの10年間
中国大返しから天下統一までの10年間は神憑っていました。
1582年(天正10年)6月13日
主君・織田信長を死へと追いやった明智光秀と戦います。
圧倒的な兵力の差があった明智光秀は、落ち武者により討たれ、3日の天下に幕を下ろします。
いわゆる「三日天下」です。
この戦いを「山崎の戦い」といいます。
明智討伐が清州会議で実権を握る材料になるわけです。
1582年(天正10年)6月27日
豊臣秀吉の交渉力が遺憾無く発揮されました。
そうです。「清州会議」です。有名ですね。
織田家家臣の重鎮であった柴田勝家、丹羽長秀、羽柴秀吉、池田恒興の4人で、織田信長の後継者を決めるために清州城で開かれた会議です。
当初、候補として挙げられたのは柴田勝家の推す信長の三男・織田信孝(神戸信孝)でした。
しかし、24歳の青年だと秀吉は実権を握れないわけです。

三法師を擁する秀吉(日本城郭資料館所蔵)
秀吉は、頭をフル回転させて考えました。
「自分を後見人になればいいのだ」と。
そこで、秀吉は信長の嫡男・織田信忠の長男・三法師(後の織田秀信)を推しました。
このとき、3歳でした。
もちろん、柴田勝家は猛反対します。
しかし、秀吉は明智討伐で戦功があったため池田恒興や丹羽長秀らが支持し、信孝を後見人にするという折衷案を提示したため、勝家も渋々同意しました。
もう、秀吉の思惑通りです。内心、ニヤニヤが止まらなかったことでしょう。
1584年(天正12年)3月から11月
後の天下人「徳川家康」とドンパチをした小牧・長久手の戦いです。
秀吉は「犬山城」を占拠し、徳川家康・織田信雄は「小牧山城」を占拠し、本陣を置きます。
同じ愛知県で両軍が睨み合い、膠着状態が続きました。
このとき、秀吉軍の兵力は約10万人に対し、家康・信雄軍の兵力は約1万6千~1万7千人です。
膠着状態が長く続いた結果、決着が着かずに、単独講和となりました。
というのも、四国の長宗我部家が四国を統一したので、小競り合いに時間を割けなかったのです。
1586年(天正14年)9月9日(四国平定と関白・太政大臣の就任)
正親町天皇から豊臣の姓を賜り、豊臣秀吉と名乗ります。
その後の、12月25日には太政大臣となり、豊臣政権を発足させることになります。
これもあらゆる準備をした結果なのです。
といのも、秀吉は四国討伐に全力を注ぐ中、二条昭実と近衛信輔と関白職争いがありました。
いわゆる、「関白相論」というやつです。
この争いに秀吉は介入し、近衛前久の猶子となり、自ら関白になりました。
もちろん、四国も平定します。
1587年(天正15年)(九州平定)
九州では、あの有名な島津家が除々に巨大になっていました。
勢力を伸ばした島津義久に圧迫された大友宗麟が、秀吉に助けを求めるために大坂まできました。
秀吉は、関白・太政大臣としての権威を振りかざして停戦命令を発しましたが、島津が無視したため、秀吉は島津を潰すことにしました。
毛利輝元、宮部継潤、宇喜多秀家ら総勢約10万人の良き戦友を引き連れ、颯爽と滅亡寸前の大友氏の前に現れ、島津を叩き潰しました。
これによって、九州も平定します。
1591年(天正19年)6月(奥州平定)
最後の最後まで手付かずであった奥州を攻めることに決めます。
その大役を息子である豊臣秀次に任せることにします。
豊臣秀次を総大将とし、総勢6万人を奥州へ派遣します。
3日で鎮圧するという荒業を見せます。
天下統一
秀吉は、奥州を平定したことで、全国を平定し、天下統一を達成し、戦国の世を終わらせました。
主君・織田信長の悲願であった天下統一を果たしたということです。
では、なぜ、10年という短い期間で天下統一をすることできたのでしょうか。
それは、秀吉の考え方にあると考えられています。
秀吉は晩年に「人を切ぬき申候事きらい申候」と語っています。
つまり、戦国武将には少ない非殲滅主義が故に、自分に歯向かった毛利氏・長宗我部氏・島津氏といった数々の大名を切腹させることなく、自らの配下へとしました。
これが短期間に天下統一を達成できた大きな理由です。
まとめ
豊臣秀吉は、農民から天下人へとなりました。
契機は、やはり織田信長に仕えたことでした。
天下人への階段を登り始めた理由は、明智光秀を討伐した山崎の戦いでした。
それからは指で数えられるほどの短い期間で全国を平定します。
その理由は、豊臣秀吉の非殲滅主義によるところが大きいです。
今回は、ジャパニーズ・ドリームの紹介で豊臣秀吉をご紹介しました。
豊臣秀吉の実質的な天下人の期間の話は、また機会があったときにします。
では、また。
天下人になった後の記事もありますので、ご覧ください。